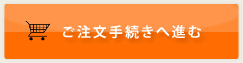書籍紹介「体質は3年で変わる」中尾光善 著
「体質は3年で変わる」
中尾光善 著 ISBN978-4-08-721269-3
最新の研究とテクノロジーによって、体質は遺伝だけでなく多様な環境との相互作用によって決まるものであり、体質に関わる遺伝子は環境の影響を受けやすいことが分かってきた。体質は変わる、変えられる。それにはどれくらいの時間がかかるのか。そこで著者が提唱するのが「体質3年説」だ。
1.体質は遺伝か環境か
(1)体質とは
医学的には体質は形質、気質、素質を総合したもので、それぞれは個体の保有している形態的、精神的、機能的性質を示す。
・形態的性質…体型や体格、顔立ちなど
・精神的性質…気性、性格など
・機能的性質…生まれ持った性質、資質、得手不得手など
(2)遺伝か環境か
・DNAの塩基配列は、1つの生物種では基本的に同じ。ヒトの場合、同じである割合は約99.9%で、違う割合はわずか0.1%程度。
・一卵性双生児はゲノムは同じですが、成長につれて外見的に微妙な違いが生まれ、性格も、かかる病気もまったく同じでないケースが多い。
2.体質を決める5つのしくみ(相互関連性)
(1)一塩基多型…血液型、毛髪や目の色を決める
(2)ポリジーン遺伝…身長、体重、血圧、知能などを決める
(3)エピゲノム…遺伝子にオン/オフの印をつける
(4)非コードRNA…遺伝子の働きに直接作用する
(5)複合的で未知なしくみの可能性…ミトコンドリア、エクソソーム、腸内フローラなど
3.3年で体質は変わる・変えられる
(1)多くの細胞は3年で入れかわる。
(2)乱れた食事習慣を3年で改善する。
(3)3年のトレーニングで病気になりにくい体をつくる。
4.ミトコンドリアの活性化(運動・寒さ・空腹が体全体の新陳代謝を促す)
(1)運動することで体内の余分なエネルギーを消費する。
(2)寒さを克服するために、体温を上げれば、蓄えたエネルギーを消費する。
(3)空腹になると蓄えたエネルギーを消費する。
生命科学が解き明かす人体の不思議
ゲノムの0.1%プラス環境因子が体質の違いを生む!!
2024年4月18日 9:01 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「「食べてはいけない」「食べてもいい」添加物」渡辺雄二 著
「「食べてはいけない」「食べてもいい」添加物」
渡辺雄二 著 ISBN978-4-479-78586-6
食品は、本来、食べ物(食品原料)からつくられるべきです。ところが、製造・加工上の都合、保存期間の延長あるいは色づけなどを目的として、食品でない添加物が使用されています。
Ⅰ 添加物の種類
1.厚労省が定めた添加物
(1)指定添加物
ほとんどは化学合成された添加物で、「自然界に存在しない化学合成物質」と「自然界に存在する成分をまねて人工的に合成した化学物質」があります。
(2)既存添加物
天然に存在する植物、海藻、昆虫、細菌、鉱物などから抽出したもの。
2.厚労省が定めた以外に使用できる添加物
(1)一般飲料添加物
ふだん私たちが食べている食品を使用したり、そこから特定の成分を抽出したもの。
(2)天然香料
ほとんど植物から抽出された香り成分
3.危険性が高い添加物
(1)指定添加物
「自然界に存在しない化学合成物質」のうち体内にとりこまれた場合、分解されにくく体内に蓄積されるものは危険性が高い。
(2)既存添加物
一見、安全であるように思われますが、食経験のない植物や海藻、細菌などから抽出したものは安全とはいえません。
Ⅱ 危険性が高い添加物と食品の具体例
1.危険性が高い添加物の具体例
(1)亜硝酸Na
・ハムやベーコンで色の黒ずみを防止するために使用される発色剤
・食品のなかのアミンと結合し、発ガン性物質に変化する。
(2)アスパルテーム
・清涼飲料やダイエット食品に使用される合成甘味料
・脳腫瘍との関係が問題視されている。
(3)ソルビン酸
・ハムやソーセージ、加工食品に用いられる保存料
・発がん性が疑われるデータがある。
(4)カラメル色素
・多くの飲みものや調味料などに色付けするために使用されている。
・発がん性をふくむものがある。
(5)調味料(アミノ酸等)
・食品に「うまみ」をつける目的で、非常に多くの食品に使用されている。
・人のよっては「中華料理店症候群」という過敏症に陥る可能性がある。
(6)香料
・お菓子や飲みものなど多数の食品に香りづけのために使用されている。
・一部危険なものがあるが、消費者には何が使用されているかわからない。
2.「食べてはいけない」食品の具体例
(1)主食系…ハムサンド、コンビニ弁当、パスタ、駅弁、カップ及び即席めん
(2)加工食品…ハム・ベーコン、ウインナーソーセージ、明太子・たらこ、福神漬、たくあん
(3)生鮮食品…輸入されたグレープフルーツ、レモン、オレンジ、ライム
(4)お菓子…ガム、豆菓子、ビーフジャーキー、サラミ、清涼菓子
(5)飲み物…炭酸飲料、コーラ、缶コーヒー、栄養ドリンク、ゼリー飲料、合成甘味料入りノンアルコールビール
(6)調味料…ダイエット甘味料、化学調味料(原材料はすべて添加物)
いつも買っているあの食品は大丈夫!?
できるだけ安全性の高い添加物が使われている食品を選択すればいい!!
2024年4月4日 9:02 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「子どもを呪う言葉 救う言葉」出口保行 著
「子どもを呪う言葉 救う言葉」
出口保行 著 ISBN978-4-8156-1653-3
1万人の犯罪者・非行少年を心理分析してわかったこと。それは、虐待や育児放棄、貧困といったわかりやすい問題だけが、犯罪や非行につながるのではない、ということ。実は、親がよかれと思って投げかけた言葉が「呪い」となって子どもを思わぬ方向に導いてしまう。心理分析で重要なのは、客観的事実のみならず、本人がどうとらえたかという「主観的現実」です。親は「確証バイアス」に陥りやすいので、意識して自分とは別の考え方を知る努力が必要です。また、方針を修正するときは、その理由を本人に説明しないと、最も重要な親子の信頼関係は築けません。
1.「みんなと仲良く」……個性を破壊する
「個性を抑える」というメッセージになることがあり、自己主張をしないで、周囲の反応を気にする生活は、自己決定力を弱めます。合わない人に合わせる必要はないし、仲良くする必要もなく、「心理的距離のとり方」を学び、当たり障りなく付き合えばいいわけです。
2.「早くしなさい」……先を読む力を破壊する
小さい子どもはみな事前予見能力が育っていませんから、なぜ急がなければいけないのかわかりません。急ぐ必要性を説明されれば、序々に自分で時間を見ながら動けるようになります。
3.「頑張りなさい」……意欲を破壊する
意欲(やる気)は自分の内側から出てくるもので、他者が植えつけることはできません。「頑張って」と言うなら、具体的に何をどうすればいいのか示すこと。また、目標を小刻みにし達成感を味わせたり(スモールステップ学習)、プロセスを褒めることで「動機づけ」にもなります。その際には「アンダーマイニング効果」に留意すること。
4.「何度言ったらわかるの」……自己肯定感を破壊する
自己肯定感は、他者との比較ではなくありのままの自分の存在に価値あると認め尊重できる感覚です。「何度言ったらわかるの」はおまえはダメだというメッセージになります。
5.「勉強しなさい」……信頼関係を破壊する
人は行動を強制されると、それに反発したくなるもの(ブーメラン効果)。「勉強しなさい」とただ伝えるのではなく、勉強の面白さを伝えることが大事です。また、親子で話題が勉強にかたより過ぎていると、それ以外の話題を子どもは避けるようになり、親子の信頼関係は破壊されます。
6.「気をつけて」……共感性を破壊する
「気をつけて!」と何でも制止すると、子どもは経験のチャンスを失います。経験はポジティブな面もネガティブな面もあり、失敗して落ち込んだりしますが、それが、成長の糧なのです。過保護・過干渉によって、人とのさまざまなリアルなコミュニケーションから育つ共感性が破壊されます。
「よかれと思って」は親の自己満足?
その子育て、一度点検してみましょう!
2024年3月21日 9:04 カテゴリー:書籍紹介